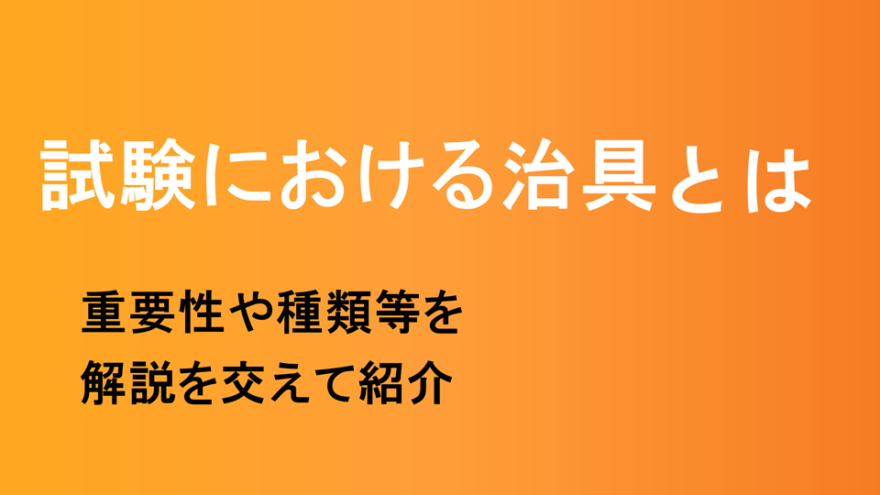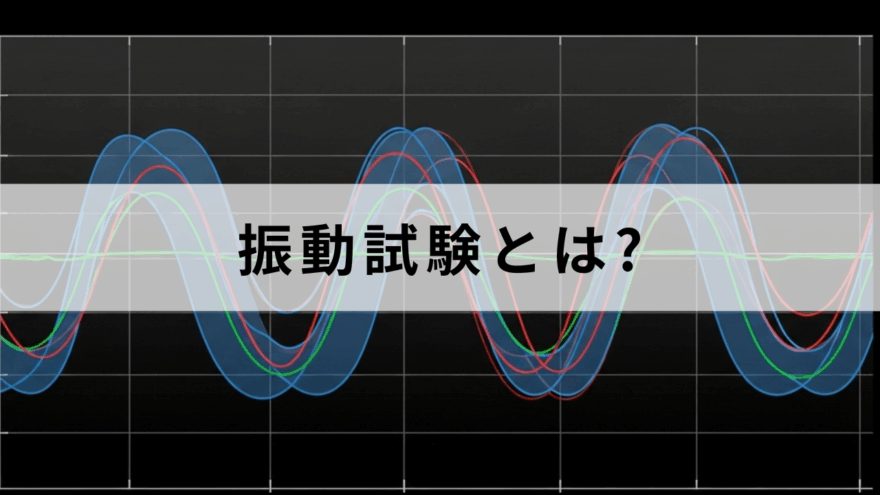コラム
Column
JISとISOの違いとは?信頼性試験における使い分け方を解説
はじめに
製品の信頼性試験や環境試験を行う際、「JISに基づいて実施してください」「ISO準拠でお願いします」といったご要望をいただくことがあります。
しかし、JISとISOは何が違って、どう使い分ければよいのかを明確に理解している方は意外と少ないかもしれません。
今回は、振動・耐久・環境試験を多く取り扱う弊社の立場から、JIS規格とISO規格の違いや使い分けの考え方について解説いたします。
JISとは?
JIS(Japanese Industrial Standards)=日本産業規格
日本国内で広く使われている国家規格であり、日本の産業製品の品質・安全性・互換性などを保つために定められています。
制定・改訂は「日本産業標準調査会(JISC)」が行い、英語訳も整備されていることが多いです。
主な特徴:
- 国内での信頼性試験では最も一般的
- 日本企業との取引や公的案件ではJISが指定されやすい
- ISOの内容をベースにしている規格も多い
ISOとは?
ISO(International Organization for Standardization)=国際標準化機構
スイス・ジュネーブに本部を持つ国際標準化団体で、世界中の技術者や専門機関が参加し、グローバルに統一された標準規格を作成しています。
主な特徴:
- 海外展開を意識する製品ではISOが重要
- 国ごとの独自解釈を減らし、国際的な信頼性を得やすい
- 試験項目や条件がより汎用的な傾向
JISとISOの違いを整理すると…
| 比較項目 | JIS | ISO |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 主に日本国内 | 国際的に共通 |
| 制定主体 | 日本政府(JIS) | 国際機関(ISO) |
| 表記例 | JIS C60068-2-6 | ISO 16750-3 |
| 目的 | 国内産業の標準化 | 世界共通の技術基準 |
| 扱いやすさ | 日本語で整備されており扱いやすい。ネット上で閲覧可能 | 最新版は有料入手が一般的 |
試験現場での“使い分け”の考え方
弊社でも、お客様からのご要望に応じてJIS規格・ISO規格どちらでも対応していますが、以下のような使い分けが多いです。
✔ 国内向け製品:
→ JISをベースにするのが一般的。日本語での規格取得がしやすく、工程との整合性も取りやすい。
✔ 輸出を含む製品(特に自動車関連や医療機器など):
→ ISOを選択することが多い。
但し、振動試験に限っていえばJIS C60068-2(ISOとほぼ共通 下記参照)か JIS D1601(国内独自でより自動車部品に特化した規格)の二択になることがほとんどです。
✔ 両方に共通点があるケース:
→ JISとISOが規格によっては同一内容(JISがISOの翻訳版)であることも多く、「JIS C60068-2」は「ISO 60068-2」と内容がほぼ一致しています。
まとめ
JISもISOも「信頼性のある製品開発」を支える大切な基準です。
試験依頼を検討する際には、製品の市場(国内/海外)や求められる品質証明レベルに応じて、適切な規格を選ぶことが重要です。
弊社では、様々な規格に対応した試験実施が可能です。
「どの規格にすべきか分からない」「選定から相談したい」という場合も、お気軽にご相談ください。